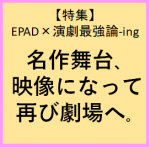【配信作品レビュー】チェルフィッチュ『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』
名作舞台、映像になって再び劇場へ。
2024.02.19
2023年度にEPADが収集した舞台作品のうち、121本が配信可能になる。語り継がれる名作舞台から、最新の若手の意欲作まで、多様な舞台が映像で見られるようになる。そのリストから1本を選んでもらい、レビューを書いてもらう「配信作品レビュー」。本稿のレビュアーは、演劇ユニット「関田育子」代表の関田育子さんです。
* * *
「経験に依拠しない言葉」が、観客の言葉と実感の結びつきを解体していく──チェルフィッチュ『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』
Text:関田育子(演出家、演劇ユニット[関田育子]主宰)
■リアリティとは異なる発話 観客の「台詞を聞き取る」行為に注目

『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』の一場面(2023年、撮影:前澤秀登)
演劇カンパニー「チェルフィッチュ」を主宰する岡田利規氏は、2021年に、日本語を母語としない俳優と演劇をつくるプロジェクトを立ち上げた。この作品は、その実践として2023年夏に上演されたものである。
2021年から2022年にかけて、4度のワークショップが開催され、3度目のワークショップの前に開かれたトークイベントのアーカイブが、YouTubeで見られる。その冒頭で、岡田氏は、「舞台上で話される日本語、ひいては世の中で使われている日本語まで敷衍(ふえん)されてもいいんですけども、その日本語というものがよりオープンになるといいのになと思っていて、演劇の実践として、ネイティブの日本語話者ではない人によって日本語が話される演劇というものが、もっともっとあっていいのではないか。そういうものが増えることが、演劇の日本語を、ひいては日本語をオープンなものにしていくことに、少しでも働きかけられるんじゃないか」という発言をしている。
「日本語がオープンになる」とは一体どのような状態であるのか、イベントの中では明確な結論には至っていなかったが、とても興味深いテーマと感じられたため、上演を記録した映像を通じて「日本語をオープンにすること」について考えたい。
舞台設定は、宇宙船イン・ビトゥイーン号の船内。4人の乗組員が「わたしたちの言葉の著しい衰退」を阻止するため、地球外生命体に言語を習得させるという政府主導のミッションを遂行しようとしている。そのほかに、船内の清掃など雑務全般を行う人間の姿をしたAIロボットが乗船している。宇宙船がワームホールを抜けて太陽系の外に出る途中、地球外知的生命体がいつの間にか船内に侵入していた。乗組員たちは、地球外知的生命体は具体的にどのタイミングで入ってきたのかを話し合う。その時の船内の様子を彼ら自身が再現しながら検証することでシーンが展開していく。
ノンネイティブの俳優が日本語を話す乗組員を演じ、ネイティブの俳優が地球外知的生命体とAIロボットを演じる。この配役から感じ取れることとして、ノンネイティブの俳優による、日本語の発話に対する新たなイントネーションやリズムの提示などはあるが、そのことよりも、私は観客が台詞(せりふ)を聞き取ることへの注力が気になった。
たとえば、舞台上には、登場人物のほかに、コーヒーマシンなどの音声アナウンスが流れるのだが、それらは機械特有の人工的な発話だった。日本語ネイティブ俳優の演じるAIロボットの発話も、日常的な会話のリアリティを再現するものではなかった。このことは、俳優がネイティブであるのかノンネイティブであるのかということ以前に、台詞を聞き取るということが演劇においてどれほどの作業なのかを浮き彫りにしていたように思う。
■「オープンになる」とは、新たな次元への解放ではないか
「日本語がオープンになるとはどのような状態なのか」を検討するにあたり、「日本語がオープンになる」とは「日本語によって、聞き手が、経験に依拠しない言葉による実感を得ること」と仮留めの定義をしてみた。
「実感」とは何か。Googleの辞書を検索すると、「物事から得る実際の感じ。また、実物に接したように、生き生きと感ずること」と定義されている。
そもそも、物事から「実際の感じ」を得るには、以前に物事を「経験」していることが前提としてある。「実物に接した」という経験がなければ、「実物に接したように」ということが認識できない。
しかし、本作では、俳優自身が、舞台上で使用する言葉(日本語)の背景に、日本語話者としての経験を持つことは、重要視されていない。むしろ、ノンネイティブとしての「経験の少なさ」が大きなポイントになっている。さらに、設定を「宇宙船」にすることによって、俳優はみな一様に「経験が不足している(実物に接した経験がない)」という状況に置かれる。
その状況下で観客は、自身の経験の有無によって獲得できる実感を求めるのではなく、今までの言葉と実感の結びつきを一度解体し、再度言葉の認識を構築していくことになる。
たとえば、作中に以下のようなシーンがある。
ある日の船内で、乗組員たちが「宇宙の音楽」とは何かを議論している。その際、比較対象として「地球の音楽」が持ち出されるが、「地球の音楽」も、個々の経験の幅を含むわけで、何を指すかは曖昧(あいまい)だ。そこで乗組員たちは、そもそも音楽は空気の振動によって伝わるものだというような、根源的な音の聞こえ方についてまで言及する。しかし、音に関するそのような共通理解は、地球外知的生命体には適用されない。宇宙空間には、空気が存在しないからだ。
このように、戯曲そのものが、私たちがある言葉に対して持っている認識を、どんどん解体していくように書かれている。
言葉と実感の結びつきを解体された観客は、「言葉(俳優の発話)」以外の舞台上にあるあらゆる要素(宇宙船を再現した舞台美術や、天井から吊るされた蛍光灯、俳優の身体など)から、別の回路を用いて、実感を得ようとする。そして、その行為が観客の中で機能したときに、初めて「実感」が更新される。
このことを私は「日本語がオープンになる」と定義する。従来の価値判断にとどまらず、新たな価値を創造する術(わざ)の一つとしての言語の解放──すなわち、“オープン”──である。
「実感の更新」が本作品における「オープンになること」だと定義したが、この「実感の更新」は、上演にとって「言葉」とは何かを、改めて考える契機になるのではないだろうか。戯曲における「言葉」の再現にとどまらず、舞台上に発話という運動として「言葉」を持ち込むことで、上演におけるイニシアティブがどこにあるのか/ないのかを考えるスタートラインに立てるような気がする。このプロジェクトから私が感じた「実感」には、そのような構造的なものも含まれる。
ここまで、仮留めの定義を述べてきたが、仮留めをはずすことができるかどうかは、本作品だけで確定できるものではない。なぜならば、本作品は大きな構想の途中にあり、今後も問題提起として展開されていくものだと感じたからだ。そして、今後の上演を観たときに、今回の仮説について再度検討したい。
—
関田育子(せきた・いくこ)/立教大学現代心理学部映像身体学科卒。2019年に演劇ユニット[関田育子]を設立。その後、「広角レンズの演劇」を提唱し、実践として演劇作品の創作を行う。「広角レンズの演劇」とは、観客が、演劇を構成するあらゆる要素(俳優の身体と劇場空間、戯曲など)を同じ解像度で知覚、認識することを目指す演劇作品のことである。『micro wave』で「かながわ短編演劇アワード2023」大賞と観客賞を同時受賞
視聴環境:有線イヤホンを接続したMacBook Air
* * *
『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』
◆上演データ
作・演出:岡田利規
出演:安藤真理、徐秋成、ティナ・ロズネル、ネス・ロケ、ロバート・ツェツシェ、米川幸リオン
2023年
吉祥寺シアター(東京)、ロームシアター京都(京都)
◆作品を視聴するには
配信先 THEATRE for ALL
公開中
製作ノート 配信先の「THEATRE for ALL」は、演劇・ダンス・映画・メディア芸術等を対象に、バリアフリー字幕・音声ガイド・手話・多言語翻訳など、観る人を限定しないアクセシビリティ対応した選りすぐりの映像配信と記事コンテンツを届けるオンライン劇場です。本稿で取り上げた『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』も、オリジナル版(英語字幕付き)に加え、日本語バリアフリー字幕と日本語音声ガイド、日本手話が施されています。