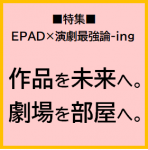【配信舞台レビュー】オル太『超衆芸術スタンドプレー』
作品を未来へ。劇場を部屋へ。
2023.02.2
世代の異なる3人の演劇人に、2022年度にEPADが収集した舞台作品の配信可能リストから1本を選び、レビューを書いてもらった。
***
淡々と物をみつめ、時間をみつめ、人をみつめている――オル太『超衆芸術スタンドプレー』
Text:山本卓卓(劇作家、演出家/範宙遊泳代表)
■アーカイブ(映像)=レプリカだとは思わない
寺山修司の天井桟敷での諸作も、ダムタイプの「S/N」も、下北沢本多劇場のこけら落とし唐十郎作「秘密の花園」も、夢の遊眠社の「小指の思い出」「半神」「贋作・桜の森の満開の下」も、蜷川幸雄演出の「ロミオとジュリエット」も、そのほか、海外の名作と呼ばれる舞台芸術のいくつか(例えばピナバウシュとかピーターブルックの諸作)も、私は映像で観てきた。だから、とくにコロナ以前、これまで散々舞台芸術の作り手たちに語られてきた「舞台芸術は映像で観たってしょうがない」だから「生(ナマ)で上演され観劇されなければならない」という”ザ・一徹”な考え方にまったく首肯できなかった。私は、目の前の作品が生=ナマであること、というよりも、その作品の鑑賞者である私自身がナマを想像し感じるのであればそれはそれでナマとして成立しているのではないか、と思ってしまう。なぜなら私はアーカイブされてきたそれら名作を通して、当時のナマを想像し、己のナマの肉体に摂取してきたからだ。だから、この体験を「映像だから本物じゃない」と他者に言われるのはかなり癪だ。リアルタイムで観ようが、映像で観ようが、その作品から得た私の体験は私のものだ。たしかにライブで観てもらわなければ、作り手のお金にならない、というかなりシビアな現実ももちろんわかっている(それは痛いほどに)。けれど舞台芸術が芸術と名乗る以上、即時的な時間軸を超えていく道程を想像せぬままでいいのだろうか、という思いが私にはつねにある。ベートーヴェンの音楽は、カフカの文学は、ゴッホの絵画は当時を生きていた消費者・鑑賞者のみに本物として存在していたのだろうか。少なくとも私は過去の作品たちによって自らが育ったことを認め、現代を生き、未来を射程に舞台芸術をつくりたいし、その時間の幅こそに希望を持ちたい。だから何度でも言うがアーカイブ(映像)=レプリカだとは思わない。範宙遊泳の作品を映像で観ようとあなたは確固たる観客だ。
で、オル太の「超衆芸術 スタンドプレー」を観た。オル太という集団の存在を知って以降そのオルタナティブな活動理念に魅力を感じていたこともあって、最新作「ニッポン・イデオロギー(仮)」を見逃していたこともあって、そしてタイトルの字面だけ見ると赤瀬川原平の「超芸術 トマソン」を空目したこともあって。
■剥奪され淘汰され付与されて誕生した“ネクスト人間”
まず第一に思ったのは演出が非常に巧みでクレバーであるということだった。舞台空間に配置されている、止まっているもの動いているもの、反復するもの横切るものゆっくり動くもの。それらが路上にありふれた建物、行き交う車、朽ちたカラーコーン、過ぎ去っていくニュース記事(情報)、捨てられたペットボトル、そうした無機質で人工的なものたち、人間によって造られつつも人間性を剥奪されたものたちが、劇場という閉鎖された社会空間に暗喩的にトレースされている。パフォーマーはみな音声としての肉声を剥奪され機械的に発話しアイコニックな動作を反復する。かと思えば後半美術作品のオークションをはじめたあたりから途端に肉感を伴い、妙に人間の存在を想起させる(セリーヌとのチャットのあたりの演技とか)。そしてラストにはマッサージ店の呼び込みバイトの「ボディケア(つまりは肉体の回復)いかがですかー?」があて先もなく響く。まるで、非人間的なものたち(人工的なものたち)が人間を妊娠し出産した過程を見てしまったような感覚になった。おかしなことだが、現代の人間は、スマホという母親の腹から産まれたのかもしれない(舞台中央の天の位置にスマホがあるし)。そんな不条理をなんだか、感じた。しかもその誕生した”ネクスト人間”は決してウェットな存在でもなければ示唆的な啓示を持った「2001年宇宙の旅」の「スターベイビー」的厳かさもない。ただただ何らかの情報を剥奪され淘汰され付与されたリサイクル品としての人間がそこにいた。これは悲しいことなのか? いやいや違う淡々としているだけだ。この作品は淡々と物をみつめ、時間をみつめ、人をみつめている。
東京オリンピックの開催が正式に延期される1ヶ月ほど前に上演されたらしい。ふーんそうかオリンピックなんて茶番もあったよな。と、時間が経ってみるとほんとうに他人事のように思えてしまう。そんなことよりボディケアだよな。剥奪され淘汰され付与される時間の中で、この作品もまた私の肉体に摂取され痛々しい部分を淡々とケアしていく。そうしてこの文頭の固有名詞のひとつにオル太が加わるのだ。それが歴史じゃん?
視聴環境:PC&ワイヤレスイヤホン

撮影:田村友一郎
作・演出・美術:オル太
演出統括:Jang-Chi
出演:新井麻弓 井上徹 川村和秀 斉藤隆文 タカハシ ‘タカカーン’ セイジ 玉木晶子 長谷川義朗 メグ忍者 山本悠
2020年
ロームシアター京都
視聴はこちらから
***
山本卓卓(やまもと・すぐる)/劇作家・演出家。範宙遊泳代表。1987年山梨県生まれ。オンラインをも創作の場とする「むこう側の演劇」や、子どもと一緒に楽しめる「シリーズ おとなもこどもも」、青少年や福祉施設に向けたワークショップ事業など、幅広いレパートリーを持つ。アジア諸国や北米で公演や国際共同制作、戯曲提供なども行い、活動の場を海外にも広げている。ACC2018グランティアーティストとして、19年9月〜20年2月にニューヨーク留学。『幼女X』でBangkok Theatre Festival 2014 最優秀脚本賞と最優秀作品賞を受賞。『バナナの花は食べられる』で第66回岸田國士戯曲賞を受賞。公益財団法人セゾン文化財団フェロー。