ゆうめい『養生』池田亮×本橋龍インタビュー
インタビュー
2024.02.14
2月17日よりザ・スズナリにて、ゆうめいの新作公演『養生』(下北沢演劇祭参加作品)が開幕する。実体験を逡巡しながら紡ぐドキュメンタリー的劇作で注目を集めた池田亮だが、今年の岸田國士戯曲賞最終候補作でもある『ハートランド』では「フィクション」という新フェーズを切り拓いた。そんな作家性の変遷を糧にしつつも、本作ではまたひとつ、既存に囚われない創作の形を模索。キャストと池田が同じ夜勤を体験し、「労働と創作を相互に取り込むこと」によってシームレスな人物と物語の造形に乗り出そうと言うのである。
画材を買うべく始めたバイトで気付けば社員になっていた男・橋本を演じるのは、池田が劇作家の同志として敬愛し、その人間性にも魅力を見出すウンゲツィーファの本橋龍。橋本と労働を共にする阿部役をゆうめいメンバーの田中祐希が、二人の後輩に当たる清水役をゆうめい・ウンゲツィーファ両作品に不可欠な俳優・黒澤多生が演じる。
仕事と生活、表現と労働、その両立の困難さを彫刻のごとく等身大で刻み付ける100分の夜勤劇。「何を、諦めればー」、「なれなかったものに、まだなりたい」という言葉の奥に浮かび上がる、やりたいこととやらなければいけないことの狭間で揺れる人物たち。親交の深いミニマムな座組だからこそ叶う3人芝居の創作について、池田亮と本橋龍に話を聞いた。

作家や俳優以前に、人間としての魅力に惹かれて
──まず、本作の構想、企画の成り立ちからお聞かせ下さい。
池田 スズナリの方に「下北沢演劇祭参加作品として何かやりませんか?」とお声かけいただいたことが最初のきっかけでした。「ぜひやりたい!」と思ったのですが、2月は台本を担当した舞台『テラヤマキャバレー』をはじめ、結構現場がかぶっていることもあって、どんな作品なら上演できるかをまず考えたんです。それで、せっかくの演劇祭なので、親交の深い少人数で今までとは少し違う実験的な作品を作ってみようと思って…。
──そこで、主演に挙がったのが本橋龍さんだったと。
池田 本橋さんと黒澤多生くんとは昨年8月にもいわき総合高校の卒業公演『Thing Thing Thing』で現場を共にしたのですが、その時間がすごく面白かったんです。多生くんは舞台監督、僕と本橋さんは脚本・演出という形だったのですが、寝泊まりしながら一緒に創作をする体験が自分にとってすごく刺激的だったんですよね。二人の劇作家が一つの演劇を作る経験はなかなかないので、新発見も多くありました。それで味をしめたじゃないですけど、元々ウンゲツィーファの演劇が好きだったこともあって、また本橋さんと一緒に何かを作りたいと思って。それで、今回は思い切って主演をやってもらおうと!
本橋 一昨年くらいから池田くんが何かと声をかけてくれたり、プライベートでも仕事や育児の話を共有する機会が結構あったんです。ただ、いわきの公演の時にすでに多生くんの出演が決まっていたこともあって、3人でいる時にもその話題が出たりしていて…。それを側で聞きながら、「2人は次も一緒にやるんだ、楽しそうだな」とちょっと羨ましかったっていう(笑)。そしたら、時間差でオファーをもらって、まさかの主演だったので驚きました。忘れられないのは、「宮崎駿が『風立ちぬ』で庵野秀明と一緒にやったのと同じ感じです!」って言われたこと(笑)。
池田 例えがビッグすぎると思われるかもしれないのですが、僕の中では本橋さん=宮崎駿という例えはしっくりきているんですよ。僕は自分の作品で泣いたり、感動しちゃうことを隠そうとしてしまうのですが、本橋さんはいわきでも結構ストレートに感情を出されていたんですよね。その光景を見て、宮﨑駿が「監督としては失格です」と言いながら『風立ちぬ』を観て泣いていた姿を思い出したんです。
本橋 あははは。そうだったんだ。でも、僕は普段は作る側の人間だし、学生時代に作った作品や人数やシーンの関係で少し出演するようなことはありましたが、他劇団で出演を担うことはほとんどないのでびっくりしました。
池田 演劇を作っている人に俳優として出てもらえたら面白そうと思ったというのもありました。でも、本橋さんには、それ以前に人間としての魅力を感じていて…。生き方とか考え方とかがすごく面白いんです。これは、田中(祐希)くんや多生くんにも通じることなのですが、職業や普段の立場を取っ払った単なる個人として話す時にも面白みを感じていて、そういった魅力が今回の話にフィットしていると感じたんです。演じていなくてもリアルというか。もちろん、同じ劇作家としてシンパシーを感じるところもあるのですが、だからこそ、仕事をしていない時間を共有した時に見える人間らしさに興味を惹かれているんですよね。
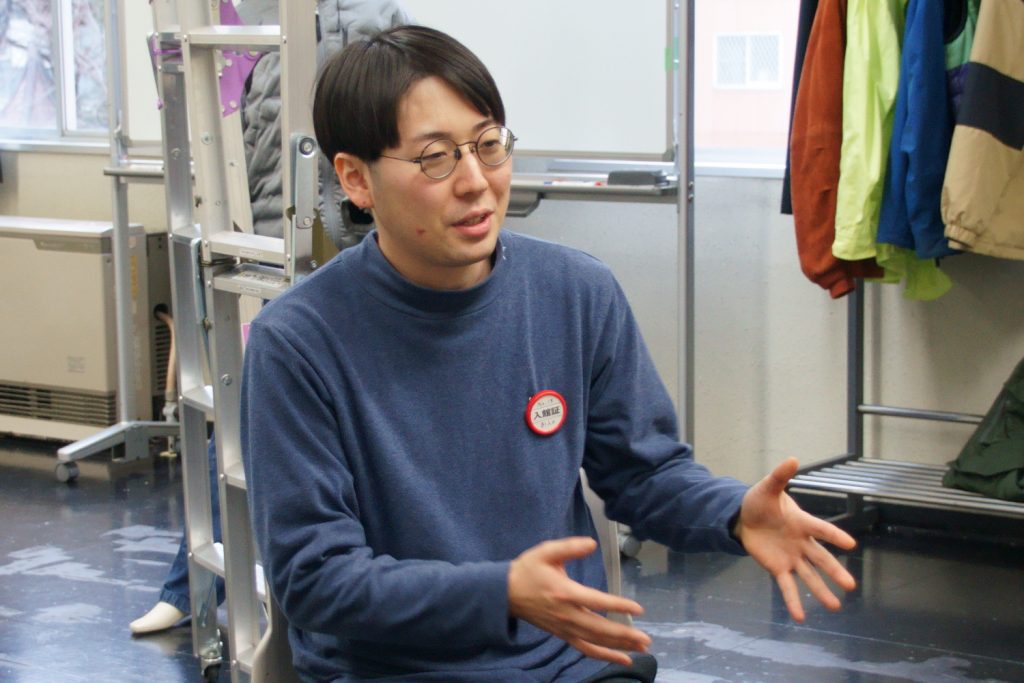
──とのことですが、本橋さんにとって池田さんはどんな人ですか?
本橋 えっと…結構ずるいやつだなって(笑)。いや、大前提にめちゃくちゃいい人間なんですよ。いろんな人を巻き込んで、自分だったらしない選択や発言をするっとやってのけてしまうというか。これはお互い様だとも思うんですけど、色んなことを悪気なく堂々とやっていて、見ている方が「それは危ないんじゃないか」って思っちゃうような感覚。だけど、そのことで人が救われていく様を見たりした時にすごく嫉妬するし、うらやましいなとも思う。勉強にもなるし、そういうのを全部置いといて“グルーヴの合う仲間”として一緒にいるなとも思う。一緒にいさせてもらえてありがたいなと常に思っています。だから、ずるいんですよ!
池田 本橋さんとは最初の出会いから結構な衝撃があったんですよね。
本橋 そうそう。僕は元々ウンゲ荘っていう2階建ての家で多生くんとルームシェアをしていて、多生くんのコミュ力が抜群に高いこともあり、演劇関係の人が度々訪れていたんですね。逆に僕は家でいる姿を人に見せたくないし、1階に人がいる状況も苦手だった。でも、シャワーが1階にあるので行くしかない。そんな状況の中、ある日僕がシャワー室から出たら、目の前に池田くんが立っていたんですよ。池田くんはそのままゆっくりとしっかりめの自己紹介を始めて、僕は真っ裸のままそれを聞いて自己紹介をし返すっていう。それが初対面でした(笑)。
池田 本橋さんがいるって聞いていたから、家に着いた時から「挨拶しなくちゃ!」とずっと思っていたんですよ。だから裸体ってことよりも、そっちの気持ちが先行しちゃって。挨拶している間も本橋さんは堂々と裸で立っているから、「こういうことで動揺しない人なら尚更ちゃんとしなきゃ!」と思って長めに…。
本橋 でも、その瞬間に「あ、この出会いは長く続きそうだ」っていう直感もあったんですよね。他にも色んな人が来たけど、そういう挨拶のシチュエーションで僕はうまくできないというか、関係が発展することもないんだけど、その時はもう文字通り生まれたままの姿だしどうしようもなかったですよね(笑)。あの時、「俺もいつか池田くんの裸を見ないといけない」と思ったよ。
池田 あははは。でも、その直感がこういう形に繋がって。2021年には芸劇eyes番外編で『Uber Boyz』という作品も一緒にやったし、いわきでは寝泊まりも共にしましたしね。
育児をきっかけに作家性は変わった?
──すごく象徴的なエピソードですね。チラッと育児の話も出ましたが、池田さんは『娘』で、本橋さんは昨年上演の『リビング・ダイニング・キッチン』で子どもの存在や育児を作品の中で描くということをされました。個人的には男性の作家であるお二人が自身の育児体験を元に作品を発表されたことや公演の環境を整える試みをされたことは新しく、いち保護者としても心強いと感じたのですが、作家としてのスタンスにおいてはどんな変化がありましたか?
池田 自分は子を持ったことによって作家としても変わらざるを得なかった気がします。「男性はこれまでどうしてこんなにも育児に参加しなかったんだろう」という社会問題が自分の中ですごく浮き彫りになったし、「どうすれば家族みんなが疲れず、傷付かずにやっていけるか」ということを気づいていく時間でもあって、それらを身をもって感じた経験は大きかった。子どもが寝てからしか母も父も動けないという状況の中で互いの仕事との両立を考えると、やっぱり無理が生じますよね。その負担の解決を考えたときに「仕事をしない/減らした方がいい」って思った時もありました。でも、そう思った時にはじめて気づけたこともあって…。これまでは一つの作品作るためにいろんなものを犠牲にしなくてはならないって思っていたけど、それはちょっと違うのかなって今の僕は思っているんですよね。日常を優先した上で作らなければ成立しないのではないか。そう思うようになったというか。
本橋 純粋に時間が限られるから、その中で作らなくてはいけない難しさはありますよね。
池田 そう。しかも、その変化が作家としては「生ぬるくなった」と思われるかもしれなくて。そういう葛藤は感じつつも、2、30年後の将来を考えたら、今は子育てをベースに生きていく時だって思うようになったんです。そんな中で「いや、親はどんどん外に働きに行くべきだよ」っていう人に会ったりもして、そういったギャップの中で気づくこともありました。僕は子の誕生を機に運転免許を取ったのですが、免許を取った後に道路標識の意味がようやくわかるみたいな、世界の見え方がガラッと変わった感覚はありましたね。子育てを中心に考えると、色んなものの見え方が変わって、それはそれで「今しか見られない世界」なのかもと思ったりもします。
本橋 池田くんと比べると、自分の場合は作家としての変化はあまり感じていないんですよね。ただ、時間の感覚が変わるっていうのはめちゃくちゃ共感します。1人の時間が本当に限られるし、下手したら1時間もない日もあるので、そんな中で時間の使い方が上手くなったような気もしています。なんだろう、今までの無駄に生きていた時間に気付かされるというか。時間が限られたからこそ整った部分もありました。

──今作は「労働」もキーワードですが、そういった意味ではクリエーション面でも「仕事と生活の両立」というのは一つのテーマだったりするのでしょうか?
池田 そうですね。本橋さんと僕がともに子育て中ということもあって、保育園迎えに行く時間まで稽古を終わらせたいとか、そういうことを考えたりもしていました。お互い子どもがいるからこそ調整しやすいというか、共有できやすい状況ではあるなと。
本橋 池田くんが子育て中ということもあって、「少人数のミニマムな形で」と声をかけてもらった時は、「子育て中の人を助けるなら、自分じゃない方がいいんじゃない?」とも思ったんですけど、たしかにそういう風通しの良さはあるかもしれないですね。それもありつつ、互いの私生活の状況が変わりながらもフラットに「また一緒にやりたい」って誘ってもらえたのはすごく嬉しかったです。
池田 アートディレクターのりょこさんから「本作にキャッチコピーがあったらいいね」と言われた時にも自分の今の生活状況について考えました。そうして、「何を、諦めればー」っていう言葉にしたのですが、これは家庭であったり、労働であったり、創作であったり、色んなことを含んでいるんですよね。「やりたいこと」と「やらなければならないこと」があって、その中で何を優先するか。全部はできない状況で何を諦めて何をやるのかっていうことは人生における普遍的なテーマだとも思っていて…。1人の人間を育てながら作品を作ることにも物語とのリンクを感じます。「誰かと出会った」その瞬間に「誰かとは出会わない」現象が起きるとか、自分の選択によって変わっていく運命っていうものをすごく意識するようになったので、今回はそんな部分を劇作に活かせたらと。
労働と創作を同じ地平から見つめて
──今回のクリエーションの特徴の一つに「働きながら作る」ということがありますよね。アルバイトでの経験を元に台本を書きつつ、実際その労働をみんなで経験しながら演劇を作る。これはゆうめいにおいても、演劇の創作全般においても全く新たな試みですね。
本橋 俳優というオファーをもらった時には正直戸惑いもあったのですが、本作が労働者、中でもアルバイターの話と聞いた時に「自分がやる必然性」みたいなものを感じました。僕自身も演劇をやりながらアルバイトで生計を立てていることもあって、役や物語との親和性を感じたんです。劇中にも描かれていますが、アルバイトをやっていると、とんでもない人と出会したりもするんですよね。作家業や演劇の現場で出会う人とバイト先という社会で出会う人たちとの考え方のギャップ、温度差がすごかったりもして…。
──なるほど。具体的にどんな違いを感じているのでしょう?
本橋 こういうことっていけないよね、気をつけたら日本はもっと良くなるよね。SNSも含めてそういったムーブメントが前者の間で起こっていることに対して、後者のコミュニティの中ではどうしようもないことがまさに起きていたりする。酷いパワハラ上司がいて、それに対してみんな辟易としているんだけど、否を唱えられるほどのエネルギーを持った人がその場にいないという現実もあるし、実際にそこに身を置いた時には自分も何も言えなくなったりもして…。日頃からそういうことを感じているので、台本を読んで共感することも多かったです。「生活や労働によって自分の中に堆積していくもの」について作家として考えていた時期でもあったので、この作品への参加は自分が今後やっていく表現にも繋がっていきそうだなって。そんな風にも思いました。
池田 すごくわかります。僕はファンタジーが大好きなのですが、観終わった後に現実が待っていることでファンタジーそのものが怖くなってしまったんですよ。稽古も現実にファンタジーを持ち込む時間なので、そういった気持ちと演出の折り合いをつけることが難しく感じた時期もありました。そう思った時に「生活と創作を同時にできたらいいな」と思って。欲を言えば、お金を稼ぎながら稽古ができたらもっといい。そんなことを考え始めたんですよね。それで、夜勤の話だし、労働と創作を兼ねてシームレスに作ってみようと。僕は美大生時代から彫刻の材料を買うために夜勤のバイトをやっていたのですが、そこが……あ、でもこれ以上バイトの話を言ったら色々とバレちゃうかもしれない…(笑)。
本橋 そっか。一部の人は知っているけど、池田くんの作家としての活動を知らない人もいるもんね。稽古の一環で労働をするって分かっちゃったら、いつも通りの現場じゃなくなっちゃう可能性もあるかも。
池田 そうなんですよ。でも、すでにホームページの公演情報とか概要読んだらバレそうではある…。
──では、そのくらいにしておきましょう(笑)。私事ですが、私も文筆業の傍らバイトをしていますし、俳優にしろ、作家にしろ、そういった状況で創作や表現を行なっている人って多いと感じます。本橋さんが「役との親和性を感じた」と仰っていたのも興味深いのですが、労働の経験が作家業や劇作に活かされるというのは結構あることでしょうか?
本橋 すごくあります。逆に、そうじゃないとできないというか、作品のために労働しているくらいのスタンスなのかも。実生活を生きるためのしんどいことは本にしてなんぼ、じゃないですけど、実際にする/しない、表に出す/出さないは別として、「創作に換えちゃおう」って思っておかないと、乗り切れないところもあります。裏を返せば、それがあることによって状況がポジティブに見えたりもする。そういうことは今まさに現在進行形で感じていますね。僕自身が「子どもができてからも作家としてのスタンスは変わらない」と思っているのもそこに通じていて、生活と表現をずっと地続きの目線で見つめているからなのかも。目の前の問題や出来事を乗り越えるために、自分の頭の中で創作や表現に変換する。ただ、その変換の作業はやっぱり公演によって自然に成される部分もあるので、こうして細々ながらも演劇を続けているのだと思います。
池田 ちなみに、タイトルを『養生』にしたのは、田中くんのバイト先での出来事を聞いたことも影響しています。そこもあんまり良くない環境で、俳優業も応援もしてくれていないし、個人的には「そんな酷いことを言ってくる人に心をすり減らすなら、一旦養生してほしいよ」と思ったというか。あと、養生テープがたくさんある風景の中で夜勤バイトをしていた実体験も理由の一つです(笑)。作品を作るためにお金を稼いでいたはずが、お金を稼ぐことがメインになって、職場の人間関係の渦にも巻き込まれ、気づけばバイトばかりしている。そんな皮肉なことがそこらじゅうで起きているからこそ、この題材を選び、描く必要があると感じました。
──聞けば聞くほどに、このメンバーだからこそできる演劇だということを感じます。最後に、そんな今回のカンパニーの強みや魅力、今後の稽古の展望や開幕に向けた意気込みをお聞かせ下さい。
池田 実体験を元に劇作をしたり、思い切ってフィクションに舵を切ったりと試行錯誤をしてきたのですが、今回はこれまでの要素を盛り沢山に詰め込みつつも、全く新しい演劇ができる気がしています。そして、それはこのメンバーだからこそ叶うこと。色んな作品や役、そして広い意味での“仕事”の現場を見てきた、引き出しの多い人たちだからこそできること。それが本作の最も大きな強みであり、見どころなのだと思います。今回僕は演出だけでなく、美大時代の経験を生かして美術面の仕掛けにも積極的に取り組んでいけたらと思っています。回遊型のツアーにするのもいいかなあとか、色んなプランを考えていますので、是非その点もお楽しみにしていただけたらと思います!
本橋 僕にとって「演劇をやること」は必然であり、好きなのですが、「演劇を観ること」はそんなに好きではないんです。だけど、演劇関係の交友の場ではそういった話題がとても多いじゃないですか。知らない固有名詞が飛び交って、それを知っていなくてはいけない空気がそこはかとなくあったりもして…。そういうコミュニティに馴染めないのもあって、同業の友人も少ないのですが、4人でいる時にはそういうことを全く感じない。何も考えず、フラットに演劇や生活の話ができるんです。それは多分、「生きること」と「演劇」が密接に絡み合っている人たちだからなのだと思います。なんだろう、うまく言えないのですが、ちょっとバンドみたいなんですよね(笑)。だから、お客さんにも演劇だからと気負わずに気軽に来ていただけたらと思っています。

取材・文:丘田ミイ子



