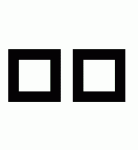ロロ いつ高シリーズファイナル 三浦直之インタビュー
インタビュー
2021.06.29

Base Ball Bearの『すべては君のせいで』という、クラスの人気者に恋をした男子の気持ちを歌った曲にこんな一節がある。「自転車通学の ヘルメットありの 君が橋の向こうからやってくる 一生、着かないと 一生、すれ違わないと わかってた僕の頬を撫でてく光のリボン」
完結編の2本立てが吉祥寺シアターで上演中のロロの『いつ高シリーズ』は、多くの人にとって、この「光のリボン」ではないだろうか。自分とは無関係のはずの、愛らしさも間の悪さも不器用な眼差しも全部まとめて青春と呼ぶしかない切ない時間が、一瞬、頬に触れて、自分も体験者になる。
大きな話になるが演劇史の中でも、ひとりの作家が10作をシリーズで完成させた例はないと思う。その創作全体について作・演出の三浦直之に聞いた。偉業と言ってもいいことを、反省まじり控えめに話す三浦のおかげで、『いつ高』シリーズは“恥ずかしくない青春演劇”のまま幕を下ろす。
── 『いつ高』シリーズ完結に際して、改めて企画の立ち上がりから振り返っていただきたいと思います。始める前に決めていたことはなんですか?
三浦 「10本で終わらせよう」というのは、当初からなんとなく決めていました。でもそれ以外はそんなに細かく考えていませんでしたね。
── 人物相関図や学校の地図は?
三浦 やりながら決めていった気がします。Vol.1の『いつだって窓際であたしたち』に、将門が太郎を見つめるシーンが出てくるんですが、その時、「10本通した最後は、このふたりが改めて出会うシーンにしよう」と決めて、それだけが全体に関わることで、それ以外は、書きながら(キャラクターやストーリーが)生まれていった感じですね。
── 三浦さんご自身、シリーズものが初めてだったとは思いますが、演劇でこういう前例はあまり記憶にありません。続編やスピンオフはあっても、10作で登場人物が有機的に繋がっているというのは稀有です。何か参考にしたものはありましたか?
三浦 漫画や小説の連作短編集──同じシリーズで、話によって視点人物が変わっていき、全部通すと一本の長い物語になる──が、まずありました。その物語単体でも完結しているけど、連なりで見ると大きなうねりが生まれるようなもの。それって、実は演劇とすごく相性がいいんじゃないかなとずっと思っていて。舞台上は限定された空間だけど、その外側をどう観客に想像させていくかが演劇だと僕は思っているから、そういう演劇の形式と、連作短編集は相性が合うはずだと思ったのがひとつ。あと僕は小さい頃からテレビドラマを観て育ったので、定期的にある物語が続いていくみたいなことを演劇でやれないかなと思ったというのがあります。
それと、このシリーズを始める直前に、サンプルの『蒲団と達磨』(’15年。作:岩松了、演出:松井周)に俳優として参加したのも大きいきっかけでした。物語が立ち上がっている、その外側にも豊かな物語がたくさんあるんだという感覚をつかんで、こういうことを自分でやりたいなと思ったんです。
── 『蒲団と達磨』で三浦さんが演じたコンちゃんは、話の終盤に登場して、短いせりふをいくつか言うだけなんだけれども、彼によってそれまで説明されていたのとはまったく違う解釈、広がりが生まれる役割を担っていましたね。そのコンちゃんのポジション的な物語を書いていきたいと思った、ということですか?
三浦 はい。コンちゃんはほとんど喋りませんから、このキャラクターはどんなヤツなんだろうと考えていったところから出発しているような気がします。
── シリーズのスタート時に主に話題を呼んだのは、高校演劇のフォーマットを厳密に取り入れたり、高校生の上演は戯曲の使用料を取らないといったことでしたが、それだけが理由ではなかったんですね。
三浦 高校演劇の審査員をやらせてもらって「自分が同じルールで作品をつくった時に、この高校生たちよりおもしろいものができるのかな?」と考えたことは確かに理由のひとつです。でもその時期、自分の中にぼんやりとしたいくつかの「こういうことがやりたい」があって、それがこのシリーズでまとまっていった感じですね。さっきお話ししたこともそうですし、当時、ダイアローグへの苦手意識があって「ダイアローグだけで作品をつくってみたらどうだろう」とか、同じタイミングで「自分が愛してきたサブカルチャーで作品をつくりたいな」とか。そういう要素がギュッとひとつになっていった。
── お話を聞いていて不思議なのが、いくつもの理由が凝縮されたスタート地点のわりに、悪い意味ではなく、作品全体に常に抜け感を保っていたことです。そのギャップは意識されましたか?
三浦 フルスケールの本公演の作品をつくるのが精神的にしんどくなって、やるごとに疲弊していく状態になった時に、そうじゃないクリエーションを自分で用意しておかないと演劇が続けられないんじゃないかという危機感があったんですね。『いつ高』は、自分の好きな物を自分の好きなように書く作品、つまり、肩の力を抜く場所にしようというのは最初に決めました。今言っていただいた「抜け感」というのは、そこから出てきているのかもしれません。
── その一方で、矛盾するようですが、緻密さも感じます。観ていて「こんな人いないよ」が「いるかも」に変わるまでに並べられた嘘が、ざっくりしているようで、実は整合性があるというか。それは劇作家としての落ち着きにも受け取れたのですが、三浦さんはそこ、無自覚ですか?
三浦 実は書く前、自分はこういう話を書くのはもっと苦手だと思っていて「自分が納得できるものを書き上げるまでに時間かかるだろうな、10本通してそういうものが書けるようになりたいな」と思っていたんです。それがvol.2の『校舎、ナイトクルージング』を書いた時に、「あれ? これは結構良いんじゃないか、なんだか書けた気がする」と思って、自分で驚いたんです(笑)。
でもそのあとは、書いていくうちにいろんな課題が見えてきて。一番悩んだのは固有名詞の扱い方の問題。始めた当初は、サブカルチャーの固有名詞をたくさん使いながら自分の好きな世界を広めていきたいという意識だったんですけど、ありがたいことに回を重ねるごとに、このシリーズを愛してくださるお客さんがついて。それはたぶん、僕と趣味の近い方がたくさん来てくれるようになって、固有名詞で客席の空気がグッと暖かくなることが出てきてうれしかったんですけど、一方で、これはいいことなんだろうかという迷いも生まれました。vol.5の『いつだって窓際でぼくたち』くらいから、固有名詞を知らない人にも届くものを自分は書けているだろうかと考えるようになりましたね。どうやって固有名詞の外側に行くか、使った固有名詞を作品のために搾取している感じにはしたくないなと。
── 三浦さんの作品はフィクション度が高いですよね。特にこの数年の本公演は、フィクションの強度を高めてその力で劇場の外のどこまで行けるか、ノンフィクションの壁を突き破れるかを問うている気がします。固有名詞は、それがアニメというフィクションの中のキャラクターでも、人間の記憶に残っていたり、影響を及ぼしている時点でノンフィクションでもある。『いつ高』シリーズにおける固有名詞の悩みは、フィクションがノンフィクションに孵化する途中段階の苦しみかもしれませんね。
三浦 話が繋がるかわからないですけど、役の名前とかもそうですけど、物語を書くって、情報を圧縮する作業だと思うんです。例えばあるキャラクターに「コンビニってさ」ではなくて「ミニストップでさ」と言わせることで、どういう性格の人なのかをお客さんに想像してもらえるように書いてきたけど、でも人ってそんなふうに何かの情報を圧縮された存在じゃないよな、みたいな。「サニーデイサービス聴きますって人、こういう人だよね」をどうやって塗り替えていくか。
── ああ、固有名詞を出すことで、作家としてはそこに頼ってしまう部分が出てくるわけですね。それと、つくり手と観客の小さなコミュニティ化を進めてしまう。
三浦 そうです。高校時代、音楽好きの友達に「サニーデイサービス聴くんだ」って言うと「あ、音楽わかってるね」みたいなコミュニケーションの取り方をされたんですけど、僕はその一方でめちゃめちゃSMAPを聴く。でもその時は「SMAPがすごい好きなんだ」と言えなかった。固有名詞を使って生まれるコードからどうやって逸脱していくか。
── その取り組みは具体的には?
三浦 vol.7の『本がまくらじゃ冬眠できない』は、僕は小説が大好きだから「この小説を引用したい、あの小説を引用したい」というものがいっぱいあるんですけど、自分の好きな小説ばかりを引用しても、僕と感性が近い人しか楽しめないと思って、自分があまり読んだことないものとか、そんなに意識を置いてないものとかも散らばせました。
vol.10の『とぶ』に関しては、さらに固有名詞を頼らないように書きました。まずは引用の仕方で、僕の好きなものだけを優先しないようにする。例えば世代を超えたり、興味のないものや距離感のある固有名詞をたくさん配置することで、僕と趣味が似た客席にならないようにしようと書き始めに決めて。
もうひとつ、vol.9『ほつれた水面で縫われたぐるみ』とvol.10ですごく考えたのは、イメージを塗り替え続けることでした。これは最近、僕自身がそのことに悩んでいるんですけど、過去との連続として自分が存在すること、過去の自分と今の自分は違うこと、このふたつは両立できるとずっと考えていて。この前やった『いつだって可笑しいほど誰もが誰か愛し愛されて第三小学校』の再演で、その戯曲が過去の自分が愛したもので書かれている。それを今の自分が振り返ると、少し違和感を持つこともある……という時に、その違和感とどう向き合うか、みたいなことを考えたんですね。その時にやっぱり過去の自分が愛したものも肯定したいし、でも今はその時の自分とは違うんだってことも肯定したいと悩んだことがあって。
それと演劇の見立てですね。脚立を山と言ったり、その次のシーンでは塔と言ったりする。そうやってイメージがどんどん上塗りされる一方で、脚立は脚立として存在して、お客さんはそれを見ている。脚立として存在していることも肯定しながら、それを別のイメージに塗り替えていくことは両立する。これは、さっき言ったことと似ているんじゃないかって。
『いつ高』もそうで、シリーズ物をやっていくと、この登場人物はこういうキャラクターだというイメージがつくられるわけですけど、シリーズを重ねていくことは、そのイメージを何回も塗り替え続けることだと思うんですよね。貼り付けた固有名詞を剥がして、また別の固有名詞を貼り付けていくという。
── それ、できている気がしますけど、どうして悩んでいるんしょう?
三浦 過去の自分も今の自分も、あまり肯定できないという自分がいまして。……自信がないんですよね。
── 三浦さんご自身の悩みですか……。いや、作品では実現されていると思います。『いつ高』シリーズは、何作か前に出てきた人がまた出てきた時に、ちゃんと時間が経っていると感じますし、実際に出てこなくて話題の中だけでも、登場人物達の生活は『いつ高』シリーズが上演されていない間も続いている感がとても強いです。連続している時間の最新形が常にそこにいます。
三浦 それならすごくうれしいです。
── 翻って、ラストの「太郎と将門が改めて出会う」ですが、ふたりの関係だけでなく『いつ高』シリーズの大きなテーマとして、最初から「眼差し」があったと思います。見つめる、そっと見る、見られる、見てもらえないなど、眼差しという点から『いつ高』を振り返っていただけますか?
三浦 眼差しに関しては、このシリーズの稽古をやっていて楽しいと思うようになったんです。あるキャラクターとあるキャラクターが話している、そこに立っているせりふのない人がどこを見ているか、何を見ているかで、こんなにシーンの意味合いが変わるんだ、ということに気付いたのが『いつ高』を始めてからでした。本公演だとどうしても、空間を動かすことに意識がいって、そこからどういう段取りで進めるかといったことに稽古の大半の時間が消費されていたので。だから、もっと俳優と密な作業をしたいなというのも『いつ高』を始めた時の目標のひとつでもあったんです。実際、このシリーズで俳優と作業していく時に、今何を見ていたか、今なんでそれを見ていたのかということを話す時間がすごく楽しかったんですよね。そこから意識的に、眼差しをどうやって作品に反映させていくかを考えてくようになりました。途中で、それが楽しくなり過ぎて、見つめるための間というものに酔い出した時期もちょっとあったりして、最近は少し落ち着いてきた気がします。
── そうした心境で考えるファイナルの眼差しは?
三浦 一番外側の眼差しは何かというと、やっぱり観客から舞台への眼差しだと思うんです。そのことについての作品になるといいなって思っています。
── それにしても6年で10本という数字は、なかなかの積み重ねです。ロロにとっても三浦さんにとっても、大きな意味のある作品になりましたね。
三浦 『いつ高』シリーズを始めてから、今までのロロとは違う観客に出会えたという手応えはすごくあります。このシリーズをきっかけに僕に映像のお仕事の話があったり、ロロを知ってくれる方も多かったですし。
── 逆にそれがプレッシャーになったり足かせになったりは?
三浦 めちゃめちゃありましたよ。『いつ高』は自分が好きなことやるために始めた場所なのに、ハードルががんがん上がってきた、みたいな(笑)。ここ何年かは、本当に終わらせられるんだろうかという気持ちでした。
── 劇団員をはじめ、俳優さんとの関係性は変わりましたか?
三浦 変わったと思います。ロロメンバーとはそれまで持っていたのとは違う共通言語をつくれました。「こういう時に何を大事にするか」みたいな場面で、昔は「元気!」「エネルギー!」だったけど(笑)、そうじゃないものを大切にしていく作業もできるようになりましたし。ロロのメンバーじゃないけど、このシリーズに参加してくれている俳優の人達も、このシリーズをすごく大事にしてくれている感じがあって、劇団の外側にゆるい繋がりみたいなものをつくれた気がするのはすごくうれしいですね。
お客さんの感想も、Twitterとか見ると、本公演は俳優の名前で「(誰々が)良かった」と言ってもらえるんですけど、『いつ高』は役名なんですよ。「シューマイが好き」「(逆)おとめが好き」とか。それは、僕からも俳優からもそのキャラクターがうまく手を離れた感じがして、うれしいです。
── 最後に、vol.9と10、同時上演ということで、何か仕掛けがあるのでしょうか?
三浦 ネタバレがあってすごく難しいんですけど。vol.10は『とぶ』とタイトルになっているように、飛ぶという上の運動、vol.9は掘るという下の運動がひとつ大きなモチーフになっています。このふたつが上手く繋がって見えるといいんですが。
それと、やっぱり高校生にやってもらえる戯曲にしたいというのが、ひとつモチベーションであるんですね。これまでより極力、固有名詞を使わずに、時代の風化に耐えられるものにしたのもそれがあったからで、『いつ高』シリーズを始めて、高校生とたくさんクリエーションする機会をもらって、その時に感じたことをなるべくそのまま物語にしていこうと思って書いたんです。高校生が実際にこれを上演する時に、(この作品のことだけでなく)演技や演劇について考える時間になるといいなと、特にvol.10はそう思って書きました。
── ありがとうございました。
取材・文:徳永京子
ロロ いつ高シリーズファイナル 2本立て公演『ほつれる水面で縫われたぐるみ』『とぶ』 公演・チケット情報は こちらから